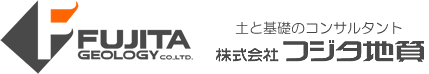今日は、机のまわりや棚などを整理しているが、いらないものがたくさんでてきた。
『一応とっておこうか』とか、『いつかは使うだろう』と思って、結局は使っていないものが多い。
以前、惚けてくると何でも溜め込むようになると聞いたことがある。捨てるという行為には、決断力がいるからということだった。
『捨てられない』ということは、『決断力がない』ということになる。
決断とは、『断つを決める』と書く。
決断力を働かせて、どんどん断っていく覚悟をもって、捨てていこうと思う。
話は変わるが、昨日の同友会例会の報告のなかで、『経営の見直しとは、何を止めるか、何をしないかを決めること』というような話があった。
捨てる、止める、断つ、これらを実行するだけでも、いろんなことが好転するような気がしてきた。
余分なものを断ち、贅肉を落とせば健康体になるのは、企業でも同じだ。
お知らせ
捨てること
ナンバープレース
今朝、土曜日の日本経済新聞NIKKEIプラス1を見ていたら、ナンバープレースというパズルが載っていたので、やってみた。
上級者8分以内、15分超は初心者、となっていたので、そんなに時間はかからないだろうと思ったが、なかなかできない。
1時間かかってもできない。
朝食をとって、さらに30分ほどやってもできない。
こんなことに時間をかけるのはもったいないからもうやめよう、と思うがやめられない。
今日は、午前中に家のなかの雑用を片付けて、午後から会社へ行って、気になっている事務処理を進めておこうと思っているのに、予定外の時間だ。
新聞は書いたり消したりして見にくくなったので、エクセルにナンバープレースを転記し、1時間ほどやってやっとできた。
出来上がってみると、やり方は間違っていなかったし、何時間もかかるほど難しいパズルではない。
パズルをやっている途中でミスや勘違いが多かったのが、時間がかかった原因だ。
急いでいい加減にやるより、間違いがないよう確実にやっていく方が、結局は速いのは仕事でも同じだ。
歯の治療
数週間前、被せていた犬歯の奥の歯(小臼歯)が痛み出したので、近所の歯医者さんで診てもらった。
歯医者さんの説明では、歯が割れているとのこと。
そういえば、歯が痛み出す前に、固いものを噛んで引っ張った時に、バキッというような感じがした。たぶんこの時にわれたのだと思う。
割れた歯は、かなり前に治療した歯で、この時に歯の神経は抜いている。
神経を抜いた歯は、水分がなくなってもろくなるらしい。
できるだけ歯は抜かずに治療しようということで、治療を続けていたが、今日金属で被せ直してこの歯の治療は一応終わった。
これで、普通に食事ができるが、他にも神経を抜いたために脆くなっている歯があると思うので、無理して固いものを噛み砕くのは避けようと思う。
できるだけ長く自分の歯をもたせたい。
寄る年並みと共に
昨日の朝、部長が
「これが机の上にあった」
と言って差し出したものは、社員Aさんの退職届であった。
部長の机の上に置いたまま、現場へでかけたとのこと。
中年も後半に差し掛かったAさんは、この猛暑のなか一生懸命働いているので、肉体的にも精神的にも疲れているのだろう、というのが部長と一致した見解である。
この日は、岡山県中小企業家同友会東備支部の役員会が予定されていたが、Aさんと話をすることの方を優先した。
夕方、Aさんの帰りを二階で仕事をしながら待っていたが、なかなか帰ってこない。
時々一階へ降りて、社員に「Aさん帰ったか。」と聞くが、「まだです。」との返事。
「Aさん現場から帰ってきたら、二階へ上がるように伝えといて。」
と言って、二階でまた仕事を続ける。
現場は県南だからそんなに遅くならないだろうと思っていたから、少し心配になりかけてきた。
そこへAさんが上がってきた。掛け時計の針は、午後7時半頃を指していた。
さっそくAさんと二人、会議用の机を挟んで座った。
私はいきなり
「やめるな!」
とAさんに言った。
「いやあ、もう、体がいうことをきかん。」
「歳じゃからしょうがねえが。どこかええ仕事があるんか。」
「ない。次の仕事のことは考えていない。」
「それなら、やめても困るじゃろうが。どこか良い就職先があるんなら仕方ないけど、体が思うように動かんというぐらいでやめるな。どこか体が悪いんか。」
「特に病気とか、体が悪いということはない。ただ、一日の仕事で、今日はこれくらいまでできるだろうと思ってやっていても、思ったところまでできない。それが自分でも情けない。」
「それは誰でも同じだ。歳をとたらとったのやり方がある。無理をせんでもええ。できるだけのことをしたらええ。」
「それでも、今日中にここまでやろうと思って頑張ったのに、夕方遅くまでやってもできないことがある。迷惑をかける。」
「だから、頑張ってもできんことはしょうがないが。無理して頑張らんでもええ。年金もらえるようになるぐらいまではやめるな。」
というような会話を繰り返した。
結局、Aさんは思いとどまった。
Aさんが、横着な人間なら引き止めなかったかも知れないが、性格は真面目で、猛暑の中を朝早くから夜遅くまでよく頑張っている。
この不景気のなか、次の仕事のことも考えずに、仕事が思うようにできないことに責任を感じて、やめると言いだすのはAさんらしい。
Aさんは、どちらかといえば、世渡りが不器用な方だと思う。このような人間を不景気の嵐が吹き荒れているなかへ、放り出すことはできない。
目標
昨日は、9月から新しい決算期に入ることに伴い、経営指針と部門目標、個人目標の発表会を行った。
今回は、事前に目標設定に関するビデオ研修を実施したうえでの目標設定である。
目標設定においては、次のようなことを重視した。
・成果(目標の到達地点)が明確であること。
・進捗状況が明確に確認できること。
・目標が、自分の努力で達成できること。(外部の要因に影響されにくいこと)
・努力しなければ達成できないが、努力すれば達成可能な目標であること。
・仕事の結果として達成できる目標であること。
以上であるが、研修ビデオで「目標は帆船の帆である」という表現をしていた通り、良い目標は個人の成長と会社の推進力になる。
昨日の個人目標発表では、難易度に問題があったり、到達地点が明確でなかったりで、質問したりコメントしたりする場面があった。
また、会社の期待と個人の目標がずれないためには、何を期待しているのかということを明確にして、面談等で個人に伝えておく必要を感じた。
全員が、良い目標、納得いく目標をたて、力を合わせて、目標の達成に全力をあげていきたい。
暑い夏と景気
一頃より幾分暑さが和らいだ気がするが、それでも暑い。
今日の週間天気予報は、岡山市の最高気温が連日36℃となっていた。
今年の寒さは、4月上旬まで続いた。
そして、梅雨はよく雨が降り、季節のメリハリのある年となっている。
冬は寒さが厳しく、、夏は猛暑の方が、景気は良いと聞いたことがあるが、この暑さが、景気に良い影響を与えてくれているだろうか。
中小企業をめぐる情勢は、依然厳しい。
数年前に、ある経済学者が講演で、
「景気は当分良くならない。少し良くなったと思えば、何かの拍子にだらだらと悪くなる。これを繰り返すだろう。」
と言ったが、リーマンショックなどを見ると、言い当てているように思う。
現在、来期の経営指針を作成中であるが、中小企業家同友会の総会議案にある『産業構造が転換期であることを自覚し、自社の周りに小さくとも堅実な市場をつくり、不況の打撃を緩和する領域を確保することが重要である』ということを踏まえて、経営計画を作成していきたい。
鳥取親戚への土産
昨日は、鳥取県東伯郡の叔母や従妹の家へ行った。
鳥取の親戚へ行く時の土産は、叔母と従妹の好みで、必ず大手まんじゅうを持っていく。
大手まんじゅうは、1837年創業の大手饅頭伊部屋の製品で、同社のホームページによれば、売上構成の90%が大手まんじゅうということである。
百七十余年、ほぼ1種類の製品で営業を続けていることは、凄いことだと思う。
新商品開発も、時代の変化に対応していくためには大切なことであるが、自社の中心とする商品に磨きをかけ、売り方を考え、自社ならではの伝統的な商品、技術に高めていくことができれば、営業していくうえで、大きな強みになると思う。
お盆休み初日
今日の午前中は、藤田家と家内の家のお墓参り。
お墓参りは、今の自分たちの命の根元である先祖に感謝を表す日であると共に、父や義父の生前のことを思い出し、今までの自分の生き方を振り返り、今の自分を見つめ、今後の自分を思う機会にもなっている。
夕方からは、貿易商の友人と、岡山駅前の居酒屋へ行った。
貿易業界も不況の影響を受けているらしく、いろいろと戦略を考えて経営されているようだ。
居酒屋を出て、岡山駅前のバス停に向かった。
友人は、バス停に着いてすぐに自宅方面に向かうバスが来たので、これに乗って帰った。
数年前までは、彼は居酒屋1軒だけで帰ることはまずなかったのだが、最近は1軒だけで帰宅しているようだ。これも不況の影響だろうか。
私は、自宅方面のバス発車時刻までは20分以上あったので、JRの電車で帰ることにした。
電車の発車時刻まで15分ほどあったので、待合席に行った。
一番端の席が濡れていたので、その隣に座った。濡れた席に座ろうとする人がいたら、濡れていることを知らせてあげようと思いながら、待合席の前に据えられたテレビを見ていたが、ほとんどの人が気がついて他の席に行った。
そのうち、太った男性が大きな荷物を持って近づいてきて、荷物を椅子の側に置くと同時に、あっと言う間もなく、濡れている席にいきなりドカと座ってしまった。
なんにも言えなかった。
結局何もしなかったことを悔いながら、3番ホームへ向かった。
再び割り箸について
昨日テレビで、「輸入品と戦う職人たち」という番組を放送していた。
この番組によると、割り箸は、建築資材を取った残りの部分で作っている。
だとすると、割り箸自体は、環境破壊にはあまり関係ないように思う。
マイ箸ブームとかで、割り箸をあまり使わないようにしようという風潮があるが、これは割り箸を作っている中小企業を倒産に追い込んだだけなのだろうか。
同番組によると、日本の職人が作った割り箸は、年輪に対し真っ直ぐに作っているので、曲がったような割れ方はしない。
割り箸は、割ったときの音と形で質が分かる。
日本の職人が作った、質の良い割り箸で日本の文化を味わうのも良いと思う。
行き過ぎたエコは、地域の経済を停滞させるだけかも知れない。
自然が循環でき、再生できる消費であれば、割り箸を使っても問題ない。再生不可能な自然環境破壊に繋がるような消費が問題だ。
経営理念社内勉強会と経営診断
先週と今週の土曜日、経営理念をテーマとした勉強会を行った。
テキストは、中小企業家同友会全国協議会前会長 赤石義博著『経営理念 人と大地がj輝く世紀に』を使用した。
経営理念を社内勉強会に取り入れた目的は
経営的視点で物事を判断してもらいたい。
経営すること、働くこと、社会貢献、生きることについて、共に深く考えてみたい。
経営理念を基に、社内の求心力を高めたい等の理由からである。
今回使用したテキスト『経営理念』によれば、経営理念を外部発進し、実践していけば、顧客や仕入れ先、地域まで求心力が働く。
地域から支持される会社づくりには、経営者が勉強し、実践していくことが不可欠なのは勿論であるが、社内みんなで勉強していくことも必要だと思う。
経営理念の勉強の後、中小企業家同友会の『企業変革プログラム』
を全員で行った。
これは、自社を自己診断することによって、経営課題を抽出し、経営指針に反映させて、ステップアップしていこうというものである。
主な診断項目は、「経営者の責任」「経営理念を実践する過程」「人を生かす経営の実践」「市場、顧客及び自社の対応状況」「付加価値を高める」である。
企業変革プログラムを使って、社員にも経営診断をしてもらうと、経営者とのズレが明確になると思ったが、社員のなかでも評価に大きな差があることが分かった。
診断結果をさらに分析して、問題点と対策、及び自社の強みをどう生かしていくか等を具体化していきたい。