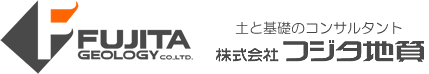昨日は、地盤改良工法と土壌汚染調査の社内勉強会を実施した。
土壌汚染物質の環境基準量は、人が70年間飲み続けて10万人に1人発症するかしないかのレベルと言われている。
この基準をどう受け止めるかは、人によってそれぞれ違うと思うが、例えばフッ素などの汚染物質が、環境基準を少し上回った量が検出されても、深刻に考えすぎない方が良い場合もあると思う。
「怖がり過ぎたり、怖がらないのは簡単だけど、適度に怖がるのは難しいということを聞いたことがある。」
と講師が言っていた。
「適度に怖がる」
これは、難しいかもしれないけれど、大切なことだと思う。
交通や現場の安全に関することも、怖がらなくては危険すぎるし、怖がり過ぎては動けない。
経営も同じだ。怖がらなくては放漫経営になりかねないし、怖がりすぎては何もできない。
怖がりすぎたら思考がストップしてしまうように思う。
適度に怖がり、理性を働かせ、安全の対策や経営の戦略をたて、時には緻密に、時には大胆に、目標に向かって行動することが大切だと思う。
お知らせ
適度に怖がる
雨の日曜出勤
久しぶりのブログ更新である。
昨夜からの雨が、一層強く降り続いている雨の日曜の朝。
会社へ出て見ると、雨合羽を着て、ふたりの社員がトラックにボーリング機械などを積み込んでいた。
明日の朝から取りかかる山口県内のボーリング調査のために、今日機材を積み込んで、出発するとのこと。
「御苦労さま」と声をかけ、事務所内にいる。
昼過ぎまで事務所内で仕事を行い、機材置き場へ行ってみると、ようやく出発の準備が終わりかけていた。
昼飯を誘って、近くの焼肉店へ行く。
焼肉店では昼定食とホルモンを注文。仕事の苦労を労いながら昼食を済ませて会社へ帰る。
再び机に向かって仕事をしていると、社員が元気な声で
「それじゃあ行ってきます。」
と言って山口県へ出かけた。
「事故のないよう気をつけて。」
と雨の中を出発するトラックを見送る。
戦争に出かける戦闘機を見送るような気分だ。
夕方まで、事務所内で仕事をしていると、一人の若手社員が帰ってきた。呉へ行ってきたとのこと。
「今日は片道千円の高速道路代で行くことができました。」
と報告あり。
土砂降りの雨の日曜日でも、社員はそれぞれ頑張っている。
社員は宝、社員は資産であることを実感する。
コスト削減の影に
トヨタなど、大企業の黒字転換のニュースが報じられている。
その理由の多くに、コスト削減の奏功があげられている。
コスト削減のやり方に、下請業者への無理な値引き要求や、あい見積で過当競争に追い込むようなことはなかったのだろうか。
もし、大企業のV字回復の影に、中小企業の利益無き回復があったのでは、本当の黒字転換とは言えないと思う。
自然界の動植物は必死に生きている
先日、稲盛和夫氏の本を読んでいたら、
「自然界では動物も植物も必死で生きている。ナマクラに生きているのは人間だけだ。」
ということが書かれていた。
たしかにその通りだと思う。
自然界の動物は、寿命で死ぬことはまずないということを聞いたことがある。天敵に襲われるか、病気やけが、あるいは高齢で餌を捕ることができなくなって飢え死にすることが多いらしい。
そんな環境の中で、動物たちは必死で天敵から身を守り、必死で餌を探し、必死で子供を育てている。
植物も、自然界ではアスファルトの割れ目から芽をだしたりしている。
自然界では、みんな必死で生きている。
人間は、いい加減に生きてもなんとか生きられる。
今回の不況は、もっと必死でやれということだと思う。
ハングリー精神
今朝、がっちりマンデーというテレビ番組に、編み機の製造メーカーである株式会社島精機製作所 島社長が出場されていた。
18歳でゴム入り軍手を作り、その後も次々とアイデアをだし、同社で作られる編み機は、世界のシェアの50%以上を占めているということである。
司会者の
「どうしてそんなに考えられるのか。」
の問いに、島社長は、
「ハングリー精神からだ。お金があると、ゆったりした気分になる。株式上場してお金が入ったが、家を建てたり寄付をしたりして、お金をおいておかないようにしている。」
というようなことを答えられていた。
テレビで見た島社長は、温和な感じの人に見えたが、すごいと思う。
たしかに、創業の時はハングリー精神は大いに持っているが、小さな成功でお金に余裕があるようになると安気な気分になり、ハングリー精神はどこかへ行ってしまう。
厳しい不況の現在、メラメラとハングリー精神が蘇っているが、良い時も悪い時も常にハングリー精神を持って挑戦し、戦い続けていくことは大切なことだと思う。
繁盛している居酒屋
昨日、岡山駅前にある大衆居酒屋へ友人のYさんと行った。
この居酒屋は、Yさんのお気に入りの店で、活気があるのが良いと言う。
結構広い店であるが、午後6時前に店へ入った時は、もう満員に近い客で賑わっていた。
席は、詰めて座ると少し窮屈だが、それに勝る良さがこの店にはあるのだろう。
客は、若い女性から、年配の夫婦づれ、中年の男性同士、大学の教授、外国人など、客層は広く、様々な人間模様が見られるような気がする。
決して綺麗な店とは言えないが、料理は多め、大きめで味は良く、割安感もあるのがこの店が繁盛している原因のひとつだと思う。
生ビール大を2杯と日本酒を少し飲んだが、生ビール大は結構量が多く、自分の適量から考えると少し飲み過ぎた。
静かな店で、落ち着いて飲むのもいいが、大入り満員の賑やかな店で飲むのも、それなりにいいなと思いながら店を出た。
圧密試験による沈下量の検討
軟弱地盤上に、木造平屋を建築するための地質調査報告書を、昨日納品させていただいた。
調査地は、軟弱地盤が深さ10m以上あるため、木造平屋建ての比較的軽量な建物でも、地盤の支持力と圧密による沈下の検討を要する。
強固な支持地盤まで支持杭を打てば問題ないが、支持地盤までの深度が深いため、平屋の場合、坪当たりの杭工事単価が全体の建築単価に対してかなり割高になるので、費用的に問題となる。
そこで、建築予定地でボーリングを行い、土を採取して圧密試験や一軸圧縮試験(土の強度を計る試験)を行なった。
圧密試験結果から沈下量を計算すると、許容沈下量をかなり下回り、べた基礎だけで、強度的にも沈下に対しても問題ないことが分かり、設計者も、圧密試験を提案した私もほっとした。
圧密試験を行う前に、直接基礎だけでも可能かどうかの推定は、地盤のデータと、経験による感である。
最近、ほとんどの所で、なんらかの地盤補強工事を実施する傾向があるように思う。
これは、建築確認申請や保証と関係しているのだと思うが、建築場所や予定建物によっては、べた基礎等の直接基礎だけでも問題ない場合もある。
軽量な構造物、特にローコスト建築を目指す場合には、地域にもよるが、本当に地盤改良工事や杭工事行う必要があるかどうか検討してみることは必要だと思う。
小さな政府、大きな政府
昨日、久しぶりに岡山県中小企業家同友会の同友会大学に出席した。
講師は岡山大学の新村教授で、最近の政治経済について分かりやすく講義してくださった。
出席者は経営者や幹部社員で、18時半から21時半まで、熱心に教授の講義を聴き、討論していた。
今回の講義のなかに、小さな政府、大きな政府がどういうことなのかというのあった。
この大きい、小さいが何に対していわれているのかよく分かっていなかったが、これは政府と市場との関係のことをいい、大きな政府とは民間経済に政府が介入する度合いが大きいということが今回の講義を聴いてよく分かった。
低賃金政策、輸出主導型は小さな政府で、高賃金政策、内需主導型は大きな政府。福祉国家は大きな政府である。
アメリカでは、共和党が小さな政府、民主党は大きな政府を目指しているが、日本では民主党も自民党も、小さな政府派と大きな政府派が混在しているらしい。
小さな政府、大きな政府、どちらも長所、短所があるが、小さな政府は、格差社会を生み出すようなので、私としては、大きな政府の方を支持したい。
井戸工事
私の自宅には、直径40mmの井戸があり、電動ポンプを取り付けて使用している。
水温は、年間通じて18度ぐらいである。
冬の井戸水は暖かく、洗車や愛犬を洗ったりするのに重宝している。
夏は、庭や路面の散水に井戸水を使うと、すぐに涼しくなる。
自分で使ってみて重宝している井戸水は、他の人が使っても便利なのではないかと思い、このたび井戸工事を積極的に販売していくことにした。
特に、比較的安価で施工できる直径40mm~50mmの、小口径井戸に力を入れていきたい。
工法は、地質調査や土壌汚染調査に用いられる機械を使用してボーリングを行い、孔内にビニールパイプを挿入して仕上げる工法と、鋼管の先に円錐コーンをつけて打ち込んでいく工法(打ち込み井戸)がある。
打ち込み井戸は、比較的狭い場所でも工事ができるので、一般民家の庭園等に適している。
井戸工事と地質調査の技術的な関連は深く、当社では、さく井(井戸)工事業の建設業許可を受け、1級さく井技能士が3名いる。
地質調査で培われた知識とさく井工事の技術を地域に生かしていきたいと思う。
価格交渉
先日の社内勉強会で学んだ価格交渉のテクニックのなかに、顧客から値切られた価格を提示されたら、わざと大げさに驚いてみせるというのがあった。
だが、自分が買い手の場合、まじめに交渉している時に、わざと「え~!」と大げさに驚いたふりをされたら気分のよいものではない。
価格より品質とか商品の特徴等をアピールし、価格を土俵にしないというのもあった。
これは、まったくその通りだと思う。
他にも、いろいろ価格交渉のテクニックがある。これらの価格交渉術は知っておいた方が良いし、駆使することも必要だと思う。
しかし、あまりうわべのテクニックに走り過ぎない方が良いとも思う。
当社の価格交渉の基本は、誠実にまじめに応対し、自社の品質、技術、特徴等や、当社を利用していただくことによって、お客様にどんなメリットがあるかを粘り強く話して理解していただき、社員の生活が守れるような価格で買ってもらうことに努力していくことだ。