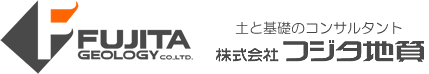この連休も、一部の社員は現場で仕事をしていた。
私の自宅から比較的近い所にあるA学院では、学校が休みの土、日、祝日の3日間でボーリング調査を実施してもらいたいとの要望があった。
このため、入社3年のH君と入社30年のKさんの2名が、勉強会のあった土曜日からA学院のボーリング調査に取りかかった。
日曜日の昼過ぎ、冷たい飲み物を持って、自転車で現場へ行ってみた。
「御苦労様」
といって、缶コーヒーとスポーツ飲料を渡した。
「ありがとうございます。」
と言って、缶コーヒーだけ飲み、二人とも直ぐに仕事を始めた。
予定の3日間で終了するのには、少し不安な状況であった。
当社の調査部長もジュースを持って、現場にきた。
調査部長が帰った後、午後4時半ごろまで現場にいて、帰宅した。
翌日の海の日、午後3時頃再び自転車で現場へ行ってみた。
入社10年以上になるM君が加わっていた。
ボーリング調査は終わり、機材撤去の準備をしていた。
無事期限内に終わりほっとした。
しばらく現場にいて、近くの自動販売機で購入した缶コーヒーを3人と飲みながら小休止し、帰宅した。
自宅で洗車し、ワックスを掛けた後、愛犬クロの散歩をしていると、ボーリング機材を積み、3人が乗ったトラックが手を振りながら通り過ぎて行った。
私は、「お疲れさまでした」と思いながら、手を挙げた。
時刻は、午後7時ごろであった。
お知らせ
連休にボーリング調査
社内勉強会
9月1日より新しい決算期が始まるので、そろそろ来期の経営指針作成に取り掛からなければならない。
経営指針づくりは、経営理念及び今期の経営戦略、経営計画を見直し、外部環境や自社の現状などの情報収集と分析を行って、社員と共に経営戦略、経営計画を作成し、目標を設定する。
昨日の勉強会のテーマは、経営指針作成に先がけ、経営理念とした。
経営理念の意味と重要性を社員に深く理解してもらうためである。
テキストは、中小企業家同友会全国協議会の赤石前会長著 「経営理念 人と大地が輝くために」。
同テキストは、中小企業家同友会の経営者を対象としているような文面が多いが、全員参加の経営を打ち出している当社としては、特に違和感はないと思う。
まず経営があり、そのなかの専門分野を受け持っていると思ってもらえれば、ものの見方、考え方も経営者に近いものになることを期待している。
安すぎても買わない
昨日、友人のI社長と久しぶりに昼食を共にしながら、聞いた話である。
I社長から、旧本社ビルを改築するために、建設会社数社から見積を取って作成した価格比較表を見せてもらった。
一番高い所と、一番安い所の、価格差は1千万円以上あった。
発注先を決定するとき、とりあえず価格が一番高い所と、一番安い所は外すことにしたと言う。
一番安い所を外したのは、たぶんそれなりの仕事しかできないだろうから、品質に不安があるという理由からだ。
官公庁の入札でも、制限価格を設けて、一定の価格より安い場合は落札させない場合が多い。
民間企業でも、I社長のように、価格だけではなく、その会社の独自性や信頼性等で発注先を決定する会社が増えれば、現在の価格破壊やデフレも収まるかも知れない。
割箸製造会社倒産から
先日、企業調査会社から地区古株の割箸製造会社倒産の情報がFAXされてきた。
安価な外国製に押されていた上、景気低迷や割箸需要の減退などが業績悪化の理由らしい。
コンビニやスーパーで食品を買ったとき、
「お箸は何本いられますか。」
と聞かれるときがある。
自宅で食べるときは、エコを考慮して
「箸はいりません。」
と言って、もらわないようにしているが、マイ箸ブームなど、エコの裏に、地域の割箸会社倒産があった。
時代の変化に対応できなかった結果だと言えばそれまでだが、企業が変わるということは、容易なことではないということかも知れない。
FMくらしき 出場
我々はジオドクター
地盤調査、特に住宅の地盤調査を行う時の基本方針とPRをまとめてみた。
・我々は、地盤の診断や地盤改良という手術もできるジオドクターです。
・むやみに手術は行いません。
・地球(ジオ)の自然保護と環境に配慮し、最もコストの掛からないのは、杭工事や地盤改良工事を行わないことです。
・地盤改良しなくても建物を維持できそうだったら、土質試験等のデータを基にその根拠を示し、建築確認申請をクリアできるようにします。
・ 500m2以下の住宅の場合、地盤改良をしなくても建物を安全に支持させることができることが証明されれば、保険会社の地盤保証を付けることができます。
・地盤改良を行えば、建て替えの時、改良体がじゃまになることがあります。
・地盤改良を行えば、建物を取り除いてさら地にした時、地中の改良体が廃棄物となって土地の評価を下げることも考えられます。
・できるだけ地球環境をそのまま残していく方針で、基礎工法の提案と地盤改良の必要性を判断します。
・やむを得ず、地盤改良や杭が必要と判断されれば、コストと安全・安心を考慮して設計し、確実に施工します。
当社は地盤改良工事も行っており、地盤改良工事はできるだけしない方が良いなどとPRすれば、自社の仕事を減らすことになりかねないが、あえて当社の基本姿勢として、上記のことを社内外に浸透させていきたい。
プロの目
先日から、自宅にある洋式トイレの便器と床の間だから水が漏れていた。
私は、てっきり便器の床から下の部分の継ぎ目あたりから漏れた水が上がってきているのだろうと思い、床と便器の間に防水材を詰め込んでみたが止まらない。
自分ではどうにもならないので、昔からよく知っている設備屋さんに電話で、
「便器から水が漏れているから見に来て欲しい。」
と言ったところ
「ウオッシュレットは付けていますか。」
と聞かれた。
「付けているけど、水が漏れて出てきているのは便器と床の間からなんだけど。」
「それは、ウオッシュレットから漏れた水が、どこかを伝っているのかも知れない。」
ということだった。
私は、半信半疑でウオッシュレットをよく点検してみた。
そうすると、確かに水が漏れているような所がある。
元栓を閉めてウオッシュレットの水を止めてみた。
そうすると床から出ていたように思っていた水が完全に止まった。
床と便器の間から水が出ていると思ったのは、思いこみであった。
プロの目は凄いと思った。
プロから見れば水漏れの原因を、まずウオッシュレットを疑ってみるのは当然かも知れないが、素人の私には思いつかなかった。
こんな日常の出来事から、専門知識や技術に磨きをかけ、経験を生かし、プロに任せた方が、安心で何倍もメリットがあると思ってもらえるようにしていくことが、業界を発展させていく上では大切なことであると思った。
先週のこと
先週はいろいろと行事が多い週だった。
6月14日月曜日は、岡山大学経済学部で、中小企業家同友会の岡山大学提供講座。
昨年と同じ、「現代中小企業論 日本経済の再生と中小企業の役割 中小企業活性化への理念型経営の実践」というテーマで講義をさせていただいた。
感想文では、「終身雇用非年功序列主義」や「社員は資産」、「民間企業で働いている人の80%が中小企業で働いている。真に国民が豊かになるには、中小企業が豊かなることが必要だ。」という言葉に興味を持って頂いた学生さんが多かったように感じた。
15日火曜日は、早朝6時より倫理法人会例会。
昼13時より岡山県中小企業家同友会正副支部長会議。
夜は同友会東備支部総会、記念講演、懇親会で、朝早くから夜遅くまで行事があり、ほとんど仕事にならなかったが、学びの多い日であった。
東備支部の記念講演は、四宮蒲鉾店の的石社長が講師で、お話から、価格決定権を持った営業を行うには、自社の商品にこだわりを持つことが大切だと感じた。
16日水曜日は、同友会倉敷支部総会へ出席するつもりであったが、時々居酒屋で交流と学び合いを行っている仲間達が、この日が都合が良いということなので、こちらへ参加することにした。
場所は、岡山駅近くのよく繁盛している居酒屋。講演での学びもいいが、居酒屋で焼き鳥と生大を飲食しながらの談義も結構学ぶところが多いものである。
17日木曜日は、岡山同友会津山支部総会の記念講演に参加した。
講師は、広島同友会の株式会社オーザック、岡崎社長。自社ならではの商品と、同友会で学ばれたことを生かし、今回の不況下でも利益をあげられているとのことで、学び真似ようと思うことが多かった。
記念講演は、帰りが遅くなるので参加せず、帰宅した。
18日金曜日は、仕事以外の行事予定なし。久しぶりに業務に専念できた。
19日土曜日は、社内勉強会。
私が、貸借対照表、損益計算書の見方、読み方を講義し、自社の過去と現在の状況を財務分析から説明した。
その後、「地盤改良工法と設計」「地盤保障の制度と仕組み」「地盤調査方法」等について学び合った。
以上、学びの中に、心地よい疲れを感じた1週間であった。
経費の見直しと営業会議
昨日の午前中は、税理士事務所の当社担当者S氏と、経費の見直しを行った。
勘定科目をひとつづつ見ていき、絶対必要な費用、あってもなくても良い費用、不必要な費用とに分類して、削減項目を洗い出した。
絶対必要な費用だけを残し、残りの費用を削減すれば、かなりの経費削減になる。
夕方からは、営業会議。
営業部から現時点までの業績報告があった後、今後の見通し、対策等を話し合った。
今後は、売上だけを重視するのではなく、仮に売上が上がらなくても、増益にもっていくにはどうすればよいか、つまり減収増益の方法を研究し、実行していくことが不可欠だと思う。
減収増益をシミュレーションして実行していくなかで、増収になれば利益が予定より多くでるので、これに越したことはない。
「お客様に満足して頂いて、売上を上げるにはどうすれば良いか。」
「売上が上がらなくても、増益にするにはどうすれば良いか。」
ということで頭の中がいっぱいの今日この頃である。
友人の励まし
岩中君という小学校5年生からの友人がいる。
岩中君は、学校卒業後配管工をしていたが、時々ボーリング調査の仕事を手伝ってもらっていた。
もう35年ほど前のことである。
春先の体がだるくなるような疲れを感じる日、私の動きが怠慢になると、一緒に仕事をしていた岩中君が、
「がんばれ、がんばれ。」
と励ましてくれていた。
岩中君は、40歳になった年の暮れに亡くなった。
それから20年の年月が流れた。
ところが最近、岩中君のニコニコした顔が頭に浮かび、
「頑張れ、頑張れ。」
と、声は聞こえないが、そう言っているように感じることがある。
「がんばれ、がんばれ」の声を感じたとき、体に力が漲ってくるような気がする。
たぶん、天国で励ましてくれているのだろうと思う。