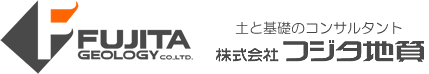明日からの富士山登山に備えて体を慣らしておこうと思い、先日の休日に、自宅から歩いて、竜ノ口登山古道から竜ノ口八幡宮、龍ノ口山(標高257m)、龍ノ口西山を経て史跡の賞田廃寺跡へ降りて、帰宅した。
5月に同じコースを通った時は2時間半で帰れたが、今回は猛暑のため4時間近くかかった。
脱水症を警戒して、途中水分補給のため休憩を多く取ったのと、暑さのためペースがゆっくりであったためである。
登口まで行く途中の工事現場で会ったガードマンと、
「今日は朝から暑いですね。36度ぐらいまで気温があがるそうですよ。」
「そうですか。仕事大変ですね。私はこの暑いなか、好きこのんで山へ登ってきます。」
「気をつけて行ってくださいよ。」
というような会話をかわして登った。
登りはじめるとしんどくて、途中竜ノ口八幡宮だけで下山しようとも思ったが、これくらいでやめたら富士山は登れないと思い、予定したコースを登って帰った。
これも、富士登山という目当てがあったから、最後までやった。
それに、富士登山がなかったら、この猛暑に山へ登ろうとすら思わなかっただろう。
何事も、目当て、目的があるからがんばれるし、大変なことにも挑戦してみようという気になる。
下山して飲んだ缶ビールが実にうまかった。
お知らせ
目当て
私心なき使命感と理念
岡山県中小企業家同友会岡山支部7月例会は、H精神医学研究所 専務理事の報告であった。
診療報酬の改定により、医療報酬が大幅に減少し、病院の経営が危機的状況に見舞われるなか、
「患者を社会復帰させたい。患者の後にいる家族のことを思うと、この病院を潰せない。」
と熱く語る専務理事のお話は感動的であった。
私心なき使命感と理念を持って、経営に取り組んでいるのを感じると、心から応援したくなる。
会社にしても、地域から「この会社を潰したくない。」と思われるような、地域になくてはならない会社になることが、本当にいい会社になる重要な要件だと改めて確信した。
社内勉強会
明日は、、社内勉強会。
当社では、数年前から毎週第3土曜日に、1日かけて業績発表と社内勉強会を実施している。
勉強会の内容は、最初の頃は技術的なものが主であったが、最近では組織運営やビジネスマナー、人間的向上に関するものを多く取り入れている。
時代の変化に対応し、潰れない強い会社にするには、技術力は勿論であるが、社長をはじめ、社員の人間的成長が欠かせない。
それに、仕事のやりがいは、生活を守ること、社会貢献、成長できること、が満たされているかどうかが大きいと思う。
「役職が上の者が成長しないと下の者はモチベーションが低下する。上の者が成長しなければ、成長していく社員はやめていく。」
と中同協の経営委員長が言われた。その通りだと思う。
人間的成長は、現在人間ができているかどうかということではなく、成長していこうと心がけているかどうかだと思う。
今日はこれから中小企業家同友会の例会で、病院の専務理事の報告。しっかり学んで明日の勉強会に生かそうと思う。
魚の値段
漁船の燃料代が高騰し、漁にでれば赤字になるという。容易に経費を商品の価格に転嫁できないのは、我々中小企業も同じである。
商品の価格は、製造経費、人件費、利益などを合計して決めるのではなく、市場で価格が決まって、その価格で生産して利益がでるようにしなければならないということだと思う。
しかし漁業に限らず、今回のように急激に燃料などの経費や材料費があがればなかなか対応できない。
国をあげて日本の漁業や農業、及び中小企業を守っていただきたいと思うと共に、「経営者である以上、いかに環境がきびしくとも、時代の変化に対応して、経営を維持し発展させる責任がある」と決意を新たに戦略を見直して挑戦していく必要を強く感じる。
事故やクレーム等の報告について
当社では、現在のところ大きな事故は幸いにもないものの、小さな事故やクレームは時々にある。
事故やクレームはあってはいけないが、あった場合にはこれを業務改善のきっかけとしたい。
クレームは処理のしかたによっては顧客にますます信頼されるチャンスになることはよく言われる。
一番問題なのは、事故やクレームがあっても、「これくらいは報告しなくていいだろう。」と自分なりの判断で報告しないことであり、お客様から話があって初めて営業の担当者や上司が知ることである。
そこで当社では、事故やクレームを起こしたことに関しては原則として処罰しないが、事故やクレームを報告しなかったり隠したりした場合は厳罰に処すとして通達した。
また、何か問題が起きた場合、誰が悪いとかではなく、現状を客観的に把握し、問題を解決し、改善していくことがビジネスにおいては大切である。
そのためにも素早い報告、連絡、相談が求められる。
中小企業家同友会定時総会
7月10日から2日間、中小企業家同友会全国協議会第40回定時総会が埼玉県で、「人と企業を育て、地域の未来を担う同友会運動を!」というスローガンのもとに開催された。
全体会のあと、18の分科会に分かれた。
私は第4分科会で、テーマは「同友会がめざす企業づくりを具体的にイメージしよう」というもので、企業変革支援プログラムという、経営の自己診断のプログラムに関する勉強会である。
報告者の最後のまとめの中で、「社長が勉強し成長していかなければ、部下のモチベーションは下がるし、成長もしない、成長する社員はやめていく。」といわれたことが心に残った。
社長や幹部の成長課題や会社の方向性を明らかにするツールがいま同友会で進めている「企業変革支援プログラム」である。
同友会内や社内でも大いに利用して、良い経営者、良い会社作りに向かって前進したい。
環境対策は倹約から
環境対策としては、以前から使っている3ナンバーの乗用車は長距離を走る時だけ使うことにして、通勤や近距離走行は昨年整備工場の経営者からもらった軽乗用車を使用している。
市街地行では、同じガソリン量で3ナンバー車の3倍近く走る。
食品は、遠くから運ばれてきたものではなく、地元でとれたものを優先的に選ぶようにしている。
また朝食を、輸入された小麦粉を使用して工場で加工されたパンとかではなく、米のご飯にすることもエコにつながると思う。
その他、使用済みのコピー用紙の裏紙の使用、弁当を買っても割り箸をもらわず自分の箸を使う、洗面所の手ふき用の紙を使わず、自分のハンカチを使うなどを心がけている。
環境対策は、エネルギーをできるだけ使わない、物を使い捨てにしない等、経済的節約に通じるので、できるだけお金を使わないことが有効な環境対策になるかも。
教育講演会
岡山県中小企業家同友会では、豊かな人間性に裏打ちされた知識と感性を持った人材を育てようと社員教育にも力を入れている。
昨日、その一環として行われる教育講演会の実行委員会があった。
本年度の教育講演会開催日は11月14日、講師はノートルダム清心学園 理事長 渡辺和子氏を予定している。
渡辺理事長の講演は、テープで一度聴かせていただいたことがある。
「相手を『許せない』ということは、『恨めしや~』という幽霊のような生き方で、私はそんな生き方はしたくない。許した時に自由な生き方ができる。」
とか、
「神様の前でお賽銭をあげて、『家内安全 商売繁盛』と願い事をする。まるで自動販売機。でも神様はその人が望むものではなく、その人に必要な物を与えてくださる。お金を入れてビールのボタンを押しても烏龍茶がでてくるかもしれない。その時その人には烏龍茶が必要なのだから、与えられたものをありがたくいただくことが大切だ。」
ということ等、ひとつのテープで多くのことを学ばせていただいた。
今から講演会が楽しみである。
四国が梅雨明け
四国の梅雨明けが発表された。例年より13日早いそうだ。
こうも早く梅雨が明けると、香川県の水不足が気になって、インターネットで早明浦ダムを検索してみると、貯水率100%となっていた。
空梅雨ではなかったということだろう。
今年は猛暑が長く続きそうなので、体調管理には十分気をつけたい。
また、暑さによる気の緩みからくる交通事故や現場での事故も心配なので、注意を徹底したい。
暑く長くなりそうな今年の夏を、気を入れて楽しみたい。
原油・穀物の値上げの影響
穀物の値上げの影響は実感としてはやや感じている程度。
原油高の方は、車の燃料代がひびいているが、まだ自社としては深刻ではない。
ずっと昔は、自動車に乗ることは贅沢なことだったし、エンゲル係数(家計の支出に占める食費の割合)も高かった。
贅沢をせず、不便でも車をできるだけ使わなければ、今回の事態は個人としては、乗り切ることができる。
車を使わなければ自然環境にもよいし、昔の日本の生活に戻るだけ。
でも、みんなが節約すれば景気はますます悪くなる。
運送業や漁業等、原油の値上げが直接影響される業界では死活問題となっている。
社会情勢や自社をとりまく経営環境も不安である
後は政治に期待するしかないのだろうか。