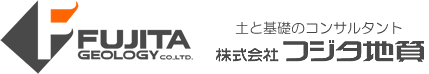今日の午後、取引していただいている会社の元社員さんと同業者の元社員さんが来社された。
ひとりは、技術の専門学校に勤務され、土木関係の学科長をされているとのこと。
前の会社では、土木設計等の技術職を勤められ、仕事の面で大変お世話になった方である。
偶然であるが、現在内定している来春卒業生は、この方の担当学科ということだ。
手みやげまでいただいて、大変恐縮だ。感謝しなければならないのはこちらの方である。
訪問していただいたもうひとりの方は、大手地質調査会社で営業されていたが、現在は地質調査とはまったく関係ない大手の会社で営業をされている。
営業職の経験を十分生かされているようだ。
当社の社員、当社の職場で技術者として、ビジネスマンとして全うしていただきたい。
しかし、もし何らかの理由で退職しなければならないことがあって退職されたとしても、当社の社員も今日来社された方々のように、新たな職場で十分に活躍できるような人間になってもらいたいし、そうなるように成長することができる職場であることが大切だと感じている。
お知らせ
新たな職場で活躍されている今日のお客様
全員参加の営業
8月で会社の決算期が終わり、来月より第33期が始まる。
それに先立ち、来期の経営指針書を作成中である。
その中の重点方針のひとつに「全員参加の営業」を掲げている。
当然ながら、いかに良い商品や優れた技術を持っていても、販売なくしては事業としてなりたたない。
『販売なくして会社なし』だ。
右肩上がりの成長期には、良い仕事さえしていればお客様からの紹介で業績は向上していった時期があったが、市場は縮小し、厳しい不況に晒されている現在では、積極的な営業展開を図り、当社の良さをアピールしていかなければ、『物心両面共に豊かさを得る』という経営理念の実現はほど遠いものになってしまう。
全員参加の営業といっても、社員全員に「仕事を受注してこい」と言う訳ではない。
お客様に感謝の気持ちを持って接し、社員それぞれにできること、例えばひとつの仕事が終了したら、現場の技術者でも
「また一緒に仕事をさせてください。」
と声をかけるということや、『お客様の声』を収集すること等を実行していく。
現場営業ができる社員は、現場営業も行う。
ある意味で、経営は数字の通りしかならないから、数字にはこだわるし、数字を追う。
しかし、その前に『お客様の心を追う』ということを浸透させていきたい。
衆議院選挙公示
昨日、衆議院選挙が公示された。
マニフェストに中小企業の法人税率を引き下げることを掲げた政党もあるが、利益がでれば決められた税は惜しみなく払うので、中小企業の利益がでやすいような環境にしていただきたいというのが、本音である。
中小企業家同友会では、「業績を外部環境のせいにせず、どんな経営環境になろうとも経営を維持し発展させていく責任が経営者にはある」と謳っている。
この言葉を胸に、日々の経営に励んでいるところであるが、政策の最優先課題は、やはり景気対策だと思う。
地域に密着し、雇用を確保し、薄利でがんばっている中小企業が発展しやすい環境にしてもらいたいと思う。
運転免許更新
今日、お盆休みを利用して運転免許更新の手続きに行った。
お盆休みは祝日ではないので、土・日曜日以外は官公庁や金融機関は通常通り業務を行っており、利用する我々にとっては便利だ。
運転免許の更新は、15年ほど前から5年毎にお盆休みに、御津の岡山県運転免許センターで行っている。
今日は、午後2時前に運転免許センターに到着、視力検査や写真撮影などの手続きを行った後、午後2時45分より30分間の講習を受講した。
そのなかで、法令が改正された点の説明があった。
車の運転に関する法令改正だから、どれも関係あり理解しておく必要はあるのだが、業務上特に関係があるのが中型免許の新設。
平成19年6月2日より後に、普通運転免許を取得した者は、最大積載量が3t以上または車両総重量が5t以上の車を運転する時は、中型ないしは大型の運転免許が必要となるので、今後トラックを購入する際には、この点も検討に入れなければならない。
講習のビデオの中で、死角に関することがあり、
『見えないこと≠いないこと』
であるといったことが印象に残った。
これは、普段意識していることであり、狭い路地を走行する時や、バックする時には、特に注意していることであるが、ちょっとした気の緩みから死角に対する注意が疎かになることもあるのではないだろうか。
死角 見えていないこと。
これは、日常生活や仕事のうえでも注意すべきことだと思う。
夜の店の経営努力
昨日、久しぶりに貿易商の友人K氏と夜の街へ出て行った。
待ち合わせ場所は、表町の居酒屋N屋さん。
K氏は、会うと「今日は儲かりましたか?」というのが、挨拶となっていたが、最近はこの言葉があまり聞かれない。
私の方から、最近の商売の状況について訪ねると
「何とかやっています。」
とのことだった。
約1時間ほど、雑談を交わしながら飲食を楽しんだ後精算。
割り勘で1人約千五百円。安いと感じた。
しかし今考えると、これが昼食だったらそんなに安いとは思わないだろう。値頃感は、場所だけではなく時間帯もある。
顧客に「安い」と感じて満足してもらうには、商品の質やサービスの追求だけではないな、と思った。
この後K氏の誘いで、西日本でチェーン展開をしている会社が運営しているキャバレーへ行った。
時間制で、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ソフトドリンクが飲み放題だったが、ビール類は発泡酒が飲み放題。別に美味しいビールが飲みたくてこの店へ来ている訳ではないので、発泡酒で十分だ。
かなり前に、この店に来た時、ここのナンバーワンという、ひとりのコンパニオンがいた。何がナンバーワンかと思えば、年齢がナンバーワン。
もう初老にさしかかろうかと思われる年代のようだったが、
「うちを指名してくださるお客様、多いんよ。」
と言われていた。同年代のお客様の指名が多かったらしいが、この方は数年前に退職されたとのことだった。
この店の印象は、接客のシステムやマナーなどがよくできていると感じた。毎日ミーティングしているということである。
不況にもかかわらず、よく繁盛している感じだった。
先ほど、この店を経営する会社のホームページを開いてみたが、
「私達は、お客様の喜び、社員の幸せ、会社の発展をテーマに、日に新たな創造と挑戦で社会に貢献しています。」と謳っている。社員の幸せを考えているところがいい。
経営理念は
一、三位一体の合致点追求の精神
一、運命共同体精神の徹底
一、革新的不断の努力
どんな業種でも、経営理念があり、経営戦略をたて、これを実践し、実践できている企業は、繁盛している所が多いのではないだろうか。(統計的数値を確認したわけではないが)
以上、昨日飲みにでた店の感想を、経営的立場から振り返ってみたが、私はいつもいろいろと分析しながら醒めた感覚で飲んでいる訳ではないので念のため。飲みにでた時は、みんなで楽しく飲むように心掛けているので、もし機会があれば、安心して誘っていただきたい。
最悪の失業率と上場企業の黒字転換
昨日の山陽新聞一面に「失業率5.4%最悪に迫る」との見出しがあり、今日の一面には「東証1部企業 最悪期脱し黒字転換」との見出しがあった。
東証1部企業が黒字転換した要因の一つに、大規模な人員削減や過剰設備の廃棄といった合理化効果があげられている。
一方失業率は、さらに悪化する可能性が高いとしている。
大企業の大規模な人員削減などによる業績回復と、大規模な人員削減などによる失業率悪化。
このことをどう捉えれば良いのだろうか。
真夏の土日を返上して
昨日の午後から今日の正午まで、吉備高原リゾートホテルにて岡山県中小企業家同友会の「組織のあり方一泊研修会」が行われた。
岡山県中小企業家同友会の役員と事務局員合わせて27名が参加し、岡山県中小企業家同友会がめざす姿や役員、事務局の役割などを根本から見直す本質的な討議が、活発に行われた。
岡山市では、昨日は花火大会が開催されるなど、夏真っ盛りの土日の休日を返上して参加されている役員と事務局員。岡山県中小企業家同友会をより良い組織にして、自分が成長し、会員が成長し、自社が発展し、会員企業が発展して、よりよい地域社会にしていこうとの志を持った方達であると思う。
主力事業の交代
今日の日本経済新聞に、「企業の『稼ぎ頭』交代」という記事が一面に掲載されていた。
記事によると、有力企業で主力事業の交代が相次いでいる。事例をあげると、
富士フイルムは、複写機・プリンターから医療関連などへ
ファーストリテイングは、ユニクロの男性向け製品から女性向けへ
ユニ・チャームは、国内子供用おむつから大人用へ
ワタミは、国内外食から介護・宅配弁当へ
日清紡は、自動車部品から太陽電池関連へ
昭和シェルは、石油から太陽電池へ
三井ハイテックは、半導体関連から環境車部品などへ、稼ぎ頭が交代する。
また、セブン&アイ・ホールディングは、スーパー事業の利益を銀行業の利益が上回った。
金融危機後の逆風下でも、事業の新陳代謝を進める企業は業績や株価が堅調だ。景気低迷で収益構造見直しを進める企業は多く、成長分野を強化する動きは広がりそうだとしている。
中小企業の方が大企業より小回りがきくと言われているが、一般的に大企業の方が、動きが早いように感じる(動きの早い中小企業も多いが)。
我々中小企業も生き残りをかけ、全社の英知を結集して時代の変化を読み取り、素早く対応していく必要があると改めて思う。
ビヤガーデンと帰りのバス停で
先週の水曜日、飲み友達数名と、山陽新聞本社の広場で行われているビヤガーデンへ行った。
最初は風が強く、紙の容器が飛ばされないよう気を使ったが、コンサートがあったり、ビールメーカーが行うクイズ付きの『ビールの美味しい飲み方説明会』があったりで、なかなか楽しい場であった。
ビールを飲みながら高い山陽新聞本社屋を見上げて、
「全国展開せず、地域密着型の企業でもこんな立派なビルを建てることができるんだな。」
と思った。
午後9時過ぎに解散し、9時20分岡山駅前発のバスで帰ろうと思い、急いでバス停に向かった。
バス停に着いてほっとしていると、白い杖をついた目の不自由なご婦人が歩いてきて、12番乗り場より少しずれたところで立ち止まったので、
「四御神行きにお乗りですか?」
と訪ねたところ、
「ここは11番ではないのですか。」
「11番乗り場は、もう少し行った所です。」
と言って、ご婦人が11番へ杖を頼りに歩いて行くのを見送った。
付いて行ったほうがいいど、もうすぐバスが来るしどうしようかな、と思っていたら、若い女性や中年の男性が次々に声をかけ、ご婦人は11番乗り場に案内されて立ち止まった。
世の中には、プラットホームから見ず知らずの他人を突き落とすような心の荒んだ人もいるけれど、ほとんどの人は、他人を思いやる優しい心の持ち主なんだなと思いながら、帰りのバスに乗り込んだ。
51年ぶりの日食
前回、日食を見たのは昭和33年。私が小学3年生の時である。
伊島小学校から、岡山大学の敷地を通って帰る途中、ランドセルから下敷きを取り出して観測したのを覚えている。
小学3年生の時の担任の先生は、父が詩吟を教えてもらったことがあるといっていた島村先生だ。
その島村先生が、
「今度岡山で日食が見られる時は、君たちは60才のおじいさん、おばあさんだ。今度の日食の時『小学校3年生の時にも、日食があったわい』って思いだすだろうね。先生はもう生きてはいないだろう。」
というようなことを仰っていた。
今日、その時がきた。
当時のことを懐かしく思いだしながら、また人生の要であったとも言える51年間を振り返りながら感無量の思いで、会社の敷地で51年後の日食を見た。