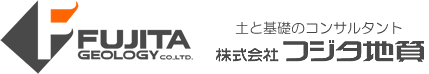朝、自転車に油をさし、空気圧はやゝ高め、サドルの高さはマニュアル通りペタルが一番下にきた時に足が若干曲がる程度に設定。
自転車は、通勤、通学用に作られた6段変速の28インチ車で、普通より少し大きめだ。
念のため、先日購入した自転車用タイヤパンドーという瞬間パンク修理剤を持っていく。
9時45分頃自宅を出発。
同行者と伊島町で待ち合わせて、10時15分頃伊島町を出発。
曲がり角は比較的多いが、自転車道の道案内の標識は分かりやすい。
笹ヶ瀬川の堤防を走り、吉備津彦神社へ到着。
茶店で休憩、アイスクリームを食べる。
吉備津彦神社から吉備津神社を通って、稲の穂が実った田園を、
「最初は心配されたが、今年も豊作みたいですね。」
というような会話を交しながら、快適に西へ走る。
造山古墳を見て、国分寺に着いたのが12時すぎ。
五重塔の軒下に彫られた干支を一通り見て、きびきび亭というバイキング形式の食堂で昼食。
満員で少し待った後、テーブルに着く。
野菜料理が中心で、肉はほとんどない。そのせいか客は年配の方が多かった。
ビールを注文。実にうまい。
一時間ほどしてきびきび亭を出発。
総社市真壁の休憩所(やよい広場)で昼寝。どれくらい寝たかよくわからない。30分以上は休んだと思う。
この後、休憩所に表示されていた清音の終点を目指して西へ進んだが、総社スポーツセンターを過ぎたあたりから標識を見失い、どこが自転車道が分からなくなった。
とりあえず清音まで行ったが、終点がよくわからないまま帰路に向かう。(帰宅後インターネットで調べたら、国交省道路局 大規模自転車道のHPには総社市役所の北で、国道180号線市役所入口の交差点あたりが起(終)点、総社市役所のHPには総社スポーツセンターが起(終)点としていた。自転車道としては総社スポーツセンターあたりが事実上の終点だと思う)
帰路の途中、作山古墳を見て、真壁の休憩所と国分寺で休憩。
伊島町に着いたのが17時頃であった。
何十年ぶりかのサイクリング。
何キロ走行したか距離計がないので正確には分からないが、自宅からの往復で55km程度は走ったと思う。
心地よい疲労感を覚える。
吉備路自転車道は、自動車と一緒に走らないため安全で走りやすく、快適であった。

吉備路自転車道 遠くに見えるのは国分寺五重塔
お知らせ
吉備路自転車道サイクリング日記
秋の夜は更けて
今の季節によくあう「倖せはここに」というハワイアン調の曲がある。
私が好きな曲のひとつで、次のような詩である。
倖せはここに 作詞・作曲 大橋節夫
秋の夜は更けて すだく虫に音に
疲れた心癒す 我が家の窓辺
静かにほのぼのと 倖せはここに
星のまばたきは 心の安らぎ
明日の夢を運ぶ やさし君が笑み
静かな我が窓辺 倖せはここに
静かに静かに 街の灯も消えた
遠い空見てごらん 明日の夢がある
小さな小さな 倖せはここに
ずいぶん昔の曲で、石原裕次郎も歌っていた。
この曲を聴くと、ほっとするような気分になる。
現状に満足し、マイホーム主義的な気分になることもある。
人間には、「足るを知る」ということで、現状に満足する部分と、
理想を追い続ける部分の両方が必要だと思う。
欲をだしたら限りがなく、もういいかと思えば成長が止まる。
私欲はほどほどに、夢や志は一生持ち続けるというのが大切だな
と、「倖せはここに」を聞きながら思った。
中小企業家同友会支部例会で学ぶ
今週は岡山県中小企業家同友会の支部例会が、目白押しだった。
火曜日は東備支部例会で、報告者は(株)S板金の社長。
波瀾万丈の青春期に父親から会社を任せられる。
仕事のほとんどが2社の下請けであったが、元請けの方針転換や内製化により、仕事がなくなる。
そこで、朝から晩まで必死に営業を行い、仕事は回復してくる。
現在では、元請けの比率がかなり上がり、優良企業ともいえる会社になっている。
社員の日報に、交換日誌のように毎日コメントを書いているとのこと。
同友会に入会し、経営指針を作成し、社員の力を引き出すようになったことも、業績と社風の向上の要因のひとつだと思う。
S社長から学ばせていただいたことは多くあるが、『本気で行動すればなんとかなる』ということが印象に残った。
水曜日は、倉敷支部例会で、報告者は広島同友会のS社社長。
S社は、事務機販売やメンテナンスを主軸にしている会社で、本社から半径20Km以内を主な商圏としている。
少ない商品で、広い商圏を確保するのは大企業。なぜなら、商品が少なければ、だれでも商品知識を覚えられるから。
中小企業は、狭い商圏で、勉強して多くの商品知識を蓄え、多くの関連商品を扱うほうが良い。その商圏範囲が半径20kmということらしい。
また、『甘え』とはどういうことかの質問に、
「甘えとは、自分の仕事の枠を自分で決めて、そこに安住して、自分はちゃんとやっているという顔をしている。」
ということ。
求める会社像は、「社員一人ひとりの『生き抜く力』を引き出す会社」ということで、『生き抜く』とはどういうことかの質問に、
「生き抜くとは、変化を創り出すことだ。」
と答えられた。
他にも多くのことを学ばせて頂いたが、長くなるので、倉敷支部例会からは、これくらいにしておく。
木曜日は、津山支部例会があったが、この日は居酒屋での勉強会を約束していた。
居酒屋勉強会には、建築業の方がいて、映画『火天の城』の話から、日本建築や宮大工のこと、火天の城に登場する岡部又右衛門のことなどが話題がでた。
金曜日は、岡山同友会のT運輸、K社長の報告。
若い社長さんだが、倒産を経験され、現在の会社はゼロどころかマイナスからの出発で、運送業でありながらこの不況時に業績をよく伸ばしている。K社長からも、多くのことを学ばせていただいたが、その一部を記述すると、
・頼まれ事は試され事。
・できない理由を言わない。
・会社が潰れる時は、必ず社長から潰れる。
・倒産防止3箇条
1.神社への参拝
2.目の前の人を喜ばす
3.魅力を付けていく
1.の神社への参拝は、神社には鏡が置いてあって、「かがみ」の「が」を抜けば「かみ」になる。つまり我を抜けば神になるということで、我を抜くと言うことらしい。
また、『やる気があれば乗り越えられる』と言われた所や、最初は社員の気持ちを考えずに働かせていたが、学ぶに従って社員を大切にするようになった所などは、東備支部例会のS社長にも共通するところである。
少々長いブログとなった。
同友会例会は、ほとんどが身近に感じる人の報告であるが、学ぶことは多い。
会員の一人ひとりは辞書の1頁である。
映画鑑賞「火天の城」
昨日、久しぶりに映画館へ行った。
映画の題名は「火天の城」で、安土城の建設を舞台に、西田敏行が演じる宮大工「岡部又右衛門」が、周囲の人々と一致団結して、五層七階の巨大な城を造るというビジョンに向かって、難題を克服しながら、安土城を完成させる物語だ。
題名から、最後は安土城の天守閣が燃えるのかなと思っていたが、感動的に完成した所で終わりだった。
心に残った場面は多くあったが、その一つを紹介すると、
工事の総棟梁は、指図(設計図)争いで決めることになった。
信長は、キリシタンの大聖堂のような吹き抜けを望んだ。
他の番匠たちは信長が望む通り吹き抜けにしたが、岡部又右衛門は吹き抜けにしなかった。
信長は激怒したが、岡部又右衛門は、
「吹き抜けにしなかったのは、天守に住まわれる信長様のお命を守るため。吹き抜けを造ると、これが火の通り道となって火の回りが速い。」
と言った。
信長は心を動かされ、岡部又右衛門は、総棟梁に任ぜられた。
これは、
「お客様の好むものを売るな、お客様のためになるものを売れ。」
という、商売戦術訓に通じるものだと思う。
他にも、木組みは人組として、職人一人ひとりを大切にして、心をひとつにしていく所など、経営的視点からみても、技術者としての視点から見ても、勉強になった映画であったし、物語としても感動的だった。
全地連「技術e-フォーラム2009」松江
9月10日、11日の2日間、全国地質調査業協会連合会が主催する全国大会 「技術e-フォーラム2009」が、島根県松江市で開催された。
今回のメインテーマは、「地域再生への取り組みー地質調査の役割ー」で、このシンポジュウムが10日の13時より開催されていたので、これに参加した。
同じ時間帯に技術発表会が行われていたが、こちらの方は受付でいただいたCD-ROM版講演集等の資料で、帰岡後勉強させていただくことにする。
シンポジュウム会場では、最初に国土交通省中国地方整備局の方より「地域再生プロジェクト」と題する基調講演があった。
続いて、「ジオパーク活動を通じた地域起こし」というテーマで、4人のパネラーによるパネルディスカッションが、16時まで行われた。
コーディネーターは大阪市立大学准教授、パネラーは隠岐の島町教育委員会や地質調査業協会会員等の方々で、産官学一体となってジオパーク活動を通じた地域起こしの取り組みや問題点について、熱心なディスカッションが行われた。
ちなみにジオパークとは、地域固有の地質や地理、生態系、歴史・文化などありのままの地域資源を素材として整備する”地球と人間のかかわり”をモチーフとした市民公園のことだ。(日本ジオパーク・モデル化研究会HPより)
シンポジュウムの後、「地質リスク学会の設立記念講演」が行われたが、こちらは中座して、展示会場へ向かった。
展示会場には、地質調査や土石流災害防止に関する機器などが展示されていた。
自社の業務に生かせるものや、新商品開発に役立つものは何かないないだろうかと、各ブースを見て回り、商品説明を聞きながらカタログや会社案内をたくさん頂いた。
今回のフォーラム参加を機会に、『地域起こし』と『自然環境を生かすこと』と『自社の地質に関する技術・知識』の合致点について模索してみたい。

セルフレジ
先日、「めざましどようび」というテレビ番組で、セルフレジが紹介されていた。
電子マネーを使って、自分でレジを済ませるというものである。
セルフレジが普及すれば、レジの仕事は減る。
スーパーとかのレジの仕事は、主婦のパートの仕事の代表的なものと思うが、セルフレジが普及すれば、地域の雇用がまた減るのだろうか。
かなり極端な発想であるが、技術やシステムが進歩して、会社に社長1人いれば、ロボットなどの機械がすべて仕事を行うようになれば、雇用はいらない。
炭坑の町が寂れたように、雇用がなくなれば、町は確実に寂れてしまう。
そうすると、生産した商品はだれが買うのだろうか。
というようなことを思ってみたが、考えすぎだろうか。
ずっと昔、私が小学生の時分であるが、オートメーションという言葉が聞かれだした頃、学校の先生が、
「オートメーション化が進めば、失業者が増えるかも知れない。」
と言われていたように記憶している。
この時は、高度経済成長により雇用は増加したと思うが、技術の発達が、産業の発達に繋がり、雇用と地域社会の発展に繋がり、幸せな社会に結びつけばよいと思う。
33期経営指針発表会
本日、午後13時30分より経営指針社内発表会を実施した。
先週の土曜日に、個人目標等は発表済みで、この時整合性のとれていない目標や、目標になっていない目標は、質問によって修正を促している。
従って、今回の個人目標発表は、目標を読み上げ、決意表明を行うだけだった。
外部環境が厳しい時期だけに、今回の経営指針作成には、例年より力が入った。
各社員の部門目標発表、個人目標発表共に熱意が強く感じられた。
最後に、来賓で出席していだだいた顧問税理士事務所の当社担当S氏に、
「真剣さと熱意が強く感じられ、今までで一番よい発表会であった。」
とのコメントを頂いた。
下記は、今期経営指針の「前期の反省と33期経営計画について」の項の一部分である。
数値目標は、前年対比から見ればこの不況時に、途方もない数値に思われますが、全社の英知を結集して取り組めば、達成は不可能ではありません。
現在、当社には素晴らしい人財が揃い、さらに来春には、2名の優秀な新規学卒者が入社される予定です。
同じ釜の飯を食う我々の仲間は、経営理念実現に向けて戦う同志であり、戦士です。
前年度、不況の影響を受けて市場は収縮しました。
この対策としては、現在の市場に合わせて会社の規模を縮小するか、それとも会社を維持し発展させることのできる市場を確保するか、の2通りが考えられます。
我々の同志を戦力であり財産と考えれば、迷わず市場の確保を選択します。
全員で力を合わせて現在の危機とも言える状況を乗り切れば、その先には輝かしい未来が開けています。
物心共に豊かな未来に向けて、全社協力体制で必ず目標を達成しましょう。
ダイエット
昨日同友会会員のSWさんのブログに、減量に関するコメントを書かして頂いたのを機会に、ダイエットについて振り返ってみた。
数年前に、体重を14kg減量した経験がある。
その時は、毎朝体重を量り、グラフを付けていった。
そうすると、グラフが下降していくのが楽しみになり、この楽しみが食べる楽しみと、歩く等の運動の億劫さを上回り、ダイエットを継続することができた。
また、食事に関しては無理をせず、外食する時はできるだけシンプルにし、余分なものを付けないようにした。
例えば、トンカツラーメンではなく、ただのラーメンだけ、うどんといなり寿司ではなく、うどんだけというようにした。
油ものはできるだけ避け、天ぷらやカツのころもは、剥がして食べた。
そうして、6月に始めたダイエットにより、その年の年末には約12kg減、翌年3月には14kg減までになった。
しばらくは減量した体重を維持していたが、あまり体重を意識しなくなったころから少しずつ増え、ここ1~2年間はほとんど体重に関して無頓着であった。
そして、気が付けば体重はほとんど元に戻っていた。
常に意識を持って、管理をしておくということが大切なのが、文字通り身にしみて分かった。
今日から再びダイエット実行を宣言する。
来期経営指針案と個人目標発表
今期も営業日としては、あと1日。
本日、来期経営指針作成全体会議として、今期業績発表、来期経営指針案及び個人目標の社内発表を行った。
来期重点方針と全社目標及び部門目標は部門長会議で調整し、各社員に発表済みである。
これを受けての個人目標発表。
ほとんどの社員が、現在置かれている経営環境と、来年度重点方針、部門目標の意味をよく理解して目標が設定されており、毎年レベルが上がっていることが感じられた。
全社目標は、今期の落ち込みをカバーするために、かなり高い数値目標となっているが、今日の個人目標発表を見れば、この不況のなかでも達成不可能ではないと、改めて思った。
個人目標もただ数字を追うような目標設定ではなく、顧客満足や当社の「安心のブランド」を普及させていくような目標も設定されている。
全社の英知を結集して、本気で行動すれば、目標は必ず達成される。
来期は、これを実証するために全力をあげることを決意する。
新たな職場で活躍されている今日のお客様
今日の午後、取引していただいている会社の元社員さんと同業者の元社員さんが来社された。
ひとりは、技術の専門学校に勤務され、土木関係の学科長をされているとのこと。
前の会社では、土木設計等の技術職を勤められ、仕事の面で大変お世話になった方である。
偶然であるが、現在内定している来春卒業生は、この方の担当学科ということだ。
手みやげまでいただいて、大変恐縮だ。感謝しなければならないのはこちらの方である。
訪問していただいたもうひとりの方は、大手地質調査会社で営業されていたが、現在は地質調査とはまったく関係ない大手の会社で営業をされている。
営業職の経験を十分生かされているようだ。
当社の社員、当社の職場で技術者として、ビジネスマンとして全うしていただきたい。
しかし、もし何らかの理由で退職しなければならないことがあって退職されたとしても、当社の社員も今日来社された方々のように、新たな職場で十分に活躍できるような人間になってもらいたいし、そうなるように成長することができる職場であることが大切だと感じている。