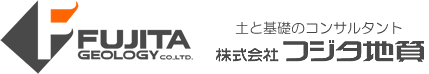先週、講演会を主体としたセミナーが、東京都港区台場に位置するホテルで3日間開催され、これに参加してきた。
インフルエンザが流行している時期であり、感染が心配であったが、うがい薬やマスクが用意されてあり、主催者の心遣いがありがたく感じられた。
講師は、97才の日野原重明氏、ワタミの渡邉美樹氏、政治評論家の三宅久之氏、75才でエレベスト登頂に成功した三浦雄一郎氏など、著明な方が多かった。
今回の講演で、
雪と欲は積もるほど道を忘れる。
人間はやって見るように作られている。 人間は、未完に生まれて未完に終わる。
愚直に一所懸命やる。難しく考えない。
この世に客に来たと思えば何の不自由もない。
トップがどう生きるかで会社は決まる。
などの他、多くの学びがあった。
また、15年前に8ヶ月間かけて行われた経営セミナーの同窓会が2日目の夜行われた。
15年もたてば変わっているだろうと思っていたが、皆あまり変わってなく、元気で活き活きと経営されている方は歳をとらないのだろうかと思った。
勧められて参加したセミナーであったが、経営のヒントが多く得られ、参加してよかったと思う。
お知らせ
新春経営者セミナー東京大会
打つ手は無限
今回の不況に対して、我が社でも手を打ってはいるが、計画通りには成果が上がっていない。
先日、ある研修機関の代表から電話があり、
「手を打っているつもりでも、案外打っていないものだ。」
と言われた。
また、先週飲み仲間数人と居酒屋へ行った時、
「現在のように世の中全体が不況になると、我々の業種では打つ手がなかなか見つからない。」
というような、話題がでた。
「打つ手は無限」という言葉はよく耳にするが、いざ手を打とうと思っても、なかなか有効な手が見つからず、閉塞感を抱いている経営者も多いのではないだろうか。
こんな時、「全社の英知を結集して経営に臨む」ということが大切であることを、先週土曜日の社内会議・勉会で実感した。
会議で、社員からの情報や意見を出し合った結果、商品・顧客の再開発等、新たな打つ手が明確になってきた。
情報が社長のところへ集まる仕組みを作り、会社の進むべき方向を打ち出し、社長が率先してアイデアをだすことは大切だと思う。
しかし、それぞれの立場で製品を作り、顧客に接して、商品・サービスを提供しているのは社員であるから、社員は顧客からの情報やアイデアをたくさん持っている。
これを集めて、知恵を出し合えば新たな打つ手は見えてくる。
社員は、会社のことをよく考えている。
「打つ手は無限」 この言葉に間違いはないと、あらためて思った。
日の出、日の入
毎朝の犬の散歩が日課となっている。
日の出の時刻が遅い今の季節は、夜が明けて出勤するまでの時間が短いので、ゆっくり散歩している時間がない。
また、早く日が暮れると屋外の作業がやりにくい。
早く日の長い時期がきてほしいと思う。
そこで、岡山の 日の出、日の入 の時刻をまとめてみた。
国立天文台のホームページによると、今年の日の出が最も遅いのは、1月3日~1月12日で7時12分。
これを過ぎると、少しずつ日の出は早くなり、2月1日で7時3分。
2月になると、ほぼ1日1分のペースで日の出時刻は早くなり、春分の日の3月20日は6時8分。
今年の日出時刻が最も早い時期は、6月5日~6月23日で、4時51分となる。
今年の日の入が最も早いのは、12月2日~12月8日で16時53分で、日の出の最も遅い日より1ヶ月ほど早い。
日の入の時刻が最も遅い時期は、6月21日~7月7日で、19時21分である。
今年の夏至は6月21日、冬至は12月22日となっている。
いくら暗く、長い夜でもその時刻がくれば、必ず夜は明ける。
人生や景気も同じだとふっと思った。
数字は後から付いてくる
経営は、ある意味で数字の通りにしかならない。
生活に困るほど窮地に陥った経験から感じることである。
しかし、いかに経済的に苦しい状況になろうとも、数字だけを追うようなことはしなかった。
顧客を追った。顧客の満足を追った。
そして数字は後から付いてきた。
苦しいからといって、形振りかまわず数字だけを追っていたら顧客は逃げ、数字も逃げていたと思う。
昨日、日本創造教育研究所から送られてきた「数字に迷うなお客様を追え」と題した田舞代表のCDを聞いて、30年前を思いだした。
恩師からの年賀状
45才の時に行われた同窓会をきっかけに、中学時代の担任の先生から、毎年年賀状を頂いている。
今年の年賀状には、次のような添え書きを頂いた。。
日本の最大の遺失物は何だったでしょう。
努力・勤勉・真面目・誠実の日本古来の徳目の喪失です。
そして、質素倹約・質実剛健の古来のライフスタイルを過去の遺物として葬り去ったのです。
倫理的価値観への敬意は何処へ?
我々の先生や父の世代は戦争を体験し、敗戦のなかから勤勉に働き、復興に力を注いでこられた。
そして、物の面では戦前の日本とは比べものにならないほど豊かになった。
我々はその恩恵を受けているといってもいいと思うが、日本古来の精神文化までは受け継ぐことができなかったのだろうか。
百年に一度の恐慌がくるかも知れないと言われている今、この時代、物心両面共に喪失してしまわないために、先生が日本の最大の遺失物として示されている努力・勤勉・真面目・誠実そして質素倹約・質実剛健のライフスタイルが必要とされていると思う。
先生は、学校卒業後何年経っても先生であり、心のよりどころの一人である。
いつまでもお元気でいてほしいと心から思う。
お疲れ様
仕事や会合などが終わった時、よくいわれる挨拶が「お疲れ様」だ。
「さよなら」は、私の年齢同士ではなんとなくあわなような気がするし、「ご苦労様」は、上の者が下の者を労う言葉と言われているから、部下や家族などに言う時以外には使いにくい。
「ありがとうございました」と言ってもおかしくない時は、「ありがとうございました」を使うようにしているが、やはり「お疲れ様」が一番使いやすくて便利な言葉のような気がする。
ところが『、「お疲れ様」と言われると、本当に疲れてくるような気がする。お元気様と言おう。』と言われる方もいる。
それはそれで結構なことだと思うのだが、先日、日本に詳しい外国人の方が、テレビで
「お疲れ様という言葉には、あなたが疲れるほど頑張っていたのを見ていましたよ。という意味がある。」
と言っていた。
ふだんあまり意識していなかったが、たしかにそんな意味で使っている。
頑張って作業を終えた人には、心から「お疲れ様でした。」という言葉がでてくる。
「お疲れ様と言われると本当に疲れてくる」と言われているのを聞いてから、「お疲れ様」は使いにくいような気がしていたが、やはり仕事や会議が終わった時の挨拶は、
「お疲れ様でした。」
でもいいと思う。
そして、心から「お疲れ様」と言えるように、相手のことをよく見ていようと思う。
少し今までの内容と外れるが、
「武士(もののふ)は己(おのれ)を知る者のために死す」
という言葉がある。
人には、自分のことを見ていて、理解してもらいたいという気持ちがあるということだと思う。
終身雇用非年功序列主義
派遣労働者を中心とした解雇、失業が連日のように報道されている。
先日のブログにも記したが、長期で派遣会社を利用している会社は、仕事が少なくなれば契約を打ち切る方針で利用している所が少なくないと思われる。
従って、景気が低迷してくれば現在のような状況になることは、予想できたことである。
多くの人が、長く幸せに暮らせる社会を創っていくには、終身雇用を前提とし、企業は社員の一生に責任を持ち、社員は会社を発展させていくことによって自分や家族も豊かになっていくという気を持ち、自分の会社を愛し、、誇りに思って働ける会社が必要だと思う。
終身雇用と年功序列がセットのように言われることがあるが、終身雇用が必ずしも年功序列ではない。終身雇用と言われた時代でも、実力重視による抜擢人事等は行われてきた。
終身雇用非年功序列というのが、私の目指すところである。
ただ、非年功序列といっても、年長者や先輩を敬う気持ちは大切にしていきたい。
企業変革支援プログラム検討プロジェクト会議
昨日、企業変革支援プログラム検討プロジェクト会議が、東京の中小企業家同友会全国協議会で、午後1時から開催された。
最初に、これまでに編集されたステップ1(導入編)の冊子作成に伴い、同友会会員の冊子製作業者を対象としたコンペの審査を行った。プロジェクトメンバーが、提出されたサンプルや見積等の評価を行ったが、どの業者もデザインや編集等が素晴らしく、甲乙付けがたい。完成が楽しみである。
続いて、ステップ2(本編)の全体像や作成スケジュール等について検討された。
ステップ2は、ステップ1で明確になった経営課題克服のためのガイドとなるものである。
中小企業家同友会は、経営者の姿勢や労使見解などの精神論的なことだけではなく、科学的に業績をあげいくことにも力を入れ、実際に企業変革プログラムのようなツールを開発し、良い会社を増やしていこうとしていることは凄いことだと、改めて感じた。
プロジェクト会議のあと、大塚駅近くの居酒屋で望年会を19時まで行い、20時10分東京駅発の新幹線で帰岡した。
人間にとって仕事とは
昨日、岡山県中小企業家同友会の社員共育大学で、「人間にとって仕事とは」というテーマで、問題提議と討議が行われた。
仕事は、暮らしの糧であるとか、人間として成長させるものであるとか、社会貢献の場であるとか等、仕事の意味はいろいろあると思うが、別の見方をすると、仕事とは人生そのものであるとも言える。
定年などで、仕事をやめると急に老け込んでくる人がいるのを見ると、特にそう思う。
ところが、仕事を楽しくやるように心掛けているとか、努力しているという人は多いが、心から仕事が楽しいと思って仕事をしている若者は、多くないはように感じた。
仕事にやりがいとか、生きがいを見いだせる人は、仕事が楽しいし、幸せだと思う。
ある農園経営者は、農業が好きで好きでたまらないらしく、「稲の苗を持ったまま田植えをする姿勢で、バタンと前のめりになって死ねたら本望だ」と言っていた。
あるボーリング会社を経営している友人は、「俺は一生穴掘りだ」といって、直径が1mもあるコアを取り出す機械を開発した。(コアとは地中の土質サンプルのことで、ボーリングでサンプリングされるコアの直径は、7cm以下が多い。コアの直径が大きいほど礫や玉石の状態を確認しやすい)
また、貿易商を営んでいる友人は、会うたびに「今日は儲かりましたか?」と言われる。決して金の亡者という感じではなく、「今日は儲かりましたか」という挨拶のなかに、我々は商人だいうことに誇りを持っているように感じられる。
この方々は、憧れて今の仕事を始めた人達ばかりではないと思うが、自分の仕事を愛し、誇りを持って一所懸命やっている。
こういう人たちを見ても、仕事とは人生そのものだと感じる。
仕事が人生そののだとすれば、仕事にやりがいや生きがいを見いだすことは、とても大切なことだ。
そのためには、自分に与えられた仕事を、中途半端な気持ちではなく、本気でやることだと思う。
天は無常無自性(自然は常に変わり、本来自分というものは無いという意味)
人は一期一会
私は一所懸命
という二宮金次郎のビデオにでてきた和尚の言葉を思いだした。
人材派遣の利用
派遣社員の契約打ち切りが社会問題として報道されている。
当社でも、かつて2名の派遣社員を利用していたが、今年の春に、1名の派遣社員の契約更新をせずに打ち切り、もう1名は派遣会社と交渉して、当社社員として雇用した。
派遣として働いている人が、みんな正社員を望んでいるわけではない。
派遣の方が精神的に束縛されないからいいという人もいた。
派遣社員は短期雇用が前提で、会社と派遣労働者との都合が合えば契約更新を続けていくし、都合が合わなくなれば契約を打ち切るというのは、当然の利用の仕方だと思う。
ただ、正社員として定職につきたいが、派遣社員としてでないと仕事が見つからないとすれば、ここに問題があると思う。
それに会社としても、正社員の産休の間だけというような臨時の利用の仕方ではなく、都合が悪くなればいつでも切ればいいというような考えで、派遣社員を雇用調整として長期間利用し、景気が悪くなれば一方的に契約解除してしまうとすれば、ここにも問題があると思う。
やむを得ず雇用調整で倒産の危機を回避しなければならない場合もあるとは思う。
しかし、人を中心とした経営ということを考えれば、雇用調整で好不況の波を乗り切るのではなく、常に安定した雇用を図り、不況がくれば社員全員の力を合わせて市場を創造していくと共に、経費の削減や業務の効率化を推進していくような経営を目指したい。